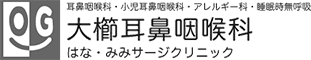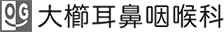コラム columns
新型コロナ感染症などのウイルス感染後の嗅覚障害が診断された場合、どのような薬物治療があるのでしょうか?
嗅覚治療には、まだこれはといった完璧な治療がなく、さまざまな施設でさままな治療が行われているのが現状です。
これから期待されている薬物治療も含め紹介していきたいと思います。
ステロイド
ウイルス感染後の嗅覚障害には、炎症が非常に強く密接に関係しております。従来嗅覚神経細胞は他の神経細胞と違って再生能力が非常に高いことが知られています。しかし、ウイルス感染による非常に強い炎症がこの再生を阻害してしまい、嗅覚が改善しなくなってしまいます。この機序は嗅覚神経に限らず顔面神経や聴覚神経でも認められる事象です。そこで、炎症が強い急性期に炎症を抑制するステロイドといった薬剤を投与することがあります。当院では1ヶ月以内の障害であれば内服も行い、3〜6ヶ月は点鼻薬として投与治療を行なったりしております。
漢方 当帰芍薬散
当帰芍薬散のうち「当帰」という成分は、血管拡張作用(末梢血流増加)、抗炎症作用、神経細胞保護作用(神経栄養因子の発現促進)などを持ち、嗅神経や嗅粘膜の血流改善・神経再生促進に寄与すると考えられています。また、「芍薬」という成分は、抗炎症作用や中枢神経保護作用を持ち、嗅神経の炎症抑制・保護作用にに貢献すると考えられています。大規模な臨床研究があまり進んでおらず、治療効果率をはっきりとデータで出すことが難しい部分もありますが、日本では嗅覚障害に最もよく出されている薬の一つです。
亜鉛製剤
血中に取り込まれた亜鉛には、神経伝達の調整や神経細胞の再生、鼻粘膜の炎症抑制効果などか報告されています。嗅神経細胞の再生に必要な元素というだけでなく、嗅覚の神経伝達を調節する「神経調節因子」としても重要です。嗅覚障害の知慮として亜鉛が体内で欠乏している症例でないと効果がないように思われますが、味覚障害に対する亜鉛製剤の投与では亜鉛欠乏の認めない症例でも効果が確認された報告があり、亜鉛製剤は嗅覚障害の方に昔からよく処方されている薬剤です。
テトラサイクリン
テトラサイクリンはもともと抗生剤として知られていますが、近年はその抗炎症作用・神経保護作用に注目が集まり、嗅覚障害のラットでの嗅上皮の神経細胞死の減少、嗅上皮の再生促進、嗅上皮での過剰な炎症の抑制効果が認められています。これにより、ウイルス感染後の嗅神経の二次的炎症性損傷を防ぎ、神経再生環境を改善する可能性があると考えられています。ただし、この作用は感染早期でないと効果がないように思われます。ウイルス感染後早期の嗅覚障害に効果がありそうです。
バルプロ酸
バルプロ酸は本来、てんかんや片頭痛の患者様に使用される薬剤ですが、その薬理作用の一つに、「ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害作用」があります。この作用は神経再生関連遺伝子の発現を促進することが知られており、実際に嗅覚障害のあるラットにおいて、バルプロ酸投与群で嗅上皮内の嗅神経細胞数の増加および嗅覚機能の回復促進が確認されています。また、ウイルスによる神経性嗅覚障害患者に対して、
バルプロ酸(1日400〜600mg程度)を数週間〜数か月投与した試験で嗅覚改善が認められた報告もあります。まだ症例数が少ないですが今後の主要薬剤となる可能性も秘めていると考えます。
まとめ
嗅覚障害の薬剤治療は目下多くの研究者がより良い治療効果を求めて研究・開発を行っている分野です。嗅覚の異常にお悩みの方はぜひとも院長にご相談ください。